|
雨夜の時鳥
忍び込んだ部屋の主は、眠っているように見えた。
枕元に膝をつくと、月明かりのない暗闇の中、そっと手を伸ばす。その手首が不意に、ガッと掴まれた。
「どうした、夜這いの真似事か? 婚前にクリステルに手を出すのなら、呪い殺してやろうと思ったのだが」
「真似事というか、その。清明、気付いてたのか」
外は、大荒れの空模様だ。
この雨音に紛れて多少の物音は聞こえまい、そう考えていたのにアテが外れた。
「気付くも何も、わしは江戸中の事象を見尽くしておる。まぁ、式神の手を借りずとも、雨戸をそんなにギシギシ鳴らされては、目も覚めようて」
清明はつまらなそうにそう呟くと、自分の上に屈み込んでいる道満の腰に手を触れるや、くるりと体勢を入れ替えた。筋骨隆々というわけでもなく、武人でもない清明に、そのような腕力があるとも思えない。多分、呪法を応用したのだろう。
「うっ、うわっ」
「欲しいのじゃろう?」
くっくっくと喉の奥で笑う。
襲うつもりが、逆に襲われる形になってしまい、パニックに陥った道満は、口をパクパクさせるしかなかった。
「そういう訳じゃ……そういうつもりじゃないんだが」
長らく対立が続いていた結野家と巳厘野家が、清明の妹・クリステルと道満の婚約によって和平するという運びになり、清明の取り成しによって、幕府にも両家共に召し抱えられることになった。だが、道満にしてみれば、幼い頃からライバル扱いされていながら遂に勝てなかった相手であり、その男にお情けで職と屋敷を与えられたようなものだ。具体的にどうしようというイメージも無かったが、何かしら仕掛けて一矢報いてやりたい、という衝動的な気持ちがあった。
だが、その当の本人にまっすぐ見据えられながら、そうと素直に白状することは、道満にはできなかった。
「ほーお?」
清明は熱のない声で呟くと、道満の夜着の衿を押し拡げた。術の修行には熱心なようだが、肉体の鍛錬までは手が回らないらしく、現れた肌身は薄い脂肪に覆われており、日を浴びていない肌はほのかに青白い。指を滑らせると、皮脂と汗が木目細かい肌をぬめらせていた。
「面倒だ」
清明が指をぱちんと鳴らすと、道満の帯が一瞬にして解け、着物が生き物のように腕を抜けて、褥の外に滑り出た。
「ひっ、本気か、清明」
「本気も何も、そもそも、お前がしようとしていたことだ」
「ちがっ、俺はこんなっ!」
片手を、腹から下へと滑らせていく。逃げられないのは、いつの間にか両手首に何か……蛇か巨大なミミズのようなものが巻き付いているからだ。いや、そのような式神に押さえ込まれずとも、道満は抵抗できなかったろう。
「考えてもみれば、クリステルが嫁入りしてしまえば、このように戯れる機会もなくなるの」
「いや、だからっ、戯れるとかそういう論点じゃ……っ!」
「ようやくお前と仲直りできそうじゃ」
そう囁いて、唇を軽く啄んでくる。
その甘い声と包み込まれる温もりに、道満の心の底で、何かがぽきりと折れたような気がした。
「痛むか? 軽くいきむようにして、開いてみよ」
ふわふわとした心地よい気分の中、清明が何を言っているのか、道満には一瞬、理解できなかった。清明の冷たい指が下腹部を這い回っているのを感じて我に返り、頬がカッと紅潮する。
「無理……そこは……」
つぷりと押し込まれて、上体が反り返った。
「いっ、痛っ……痛いっ」
「直によくなる」
あやすように口吸いを繰り返しながら、内側をまさぐる。
「んぁっ……あ……」
「ここか?」
指先に触れると激しく反応する個所を探り当て、執拗にその一点を嬲ってやる。
「あ……そこは……んっ」
「よいよい、声をあげてもこの嵐だ、外には聞こえぬ。我慢せず啼くがよい」
腕を固定されていて切ないのか、代わりに脚を清明の腰に巻き付けてきた。
「これ、そんなことをしては、わしが動けぬではないか。それとも、わしに可愛がられるのは、不服か?」
ふるふると首を振り、ゆっくりと脚を下ろす。代わりにより刺激を求めてか、腰が浮いてゆるゆると動いていた。
「いい子じゃ」
指を抜くと、喪失感からか道満が熱っぽい溜め息を吐く。清明も己の夜着を脱ぎ落とした。だが、清明が己の先端を入口に押し付けた時に、ハッとして「いや、それは無理だ」と喚いた。
「先ほどまで、散々よがっていたろうが。気持ち良かったじゃろう?」
「いや、これは無理、頼む、許してくれ」
「往生際が悪いの。観念せい」
根本を掴んで位置を定めると、腰をズイッと進めた。
「いっ……痛っ……無理っ……」
先端も入りきらぬうちから、悲鳴をあげて身をよじっている。顔を覗き込むと、涙が筋を作って伝っていた。それを手指で拭ってやると、痛みを堪えているのか硬く閉じられた目蓋の上にも、軽く唇を落としてやった。
「暴れると余計に痛むぞ。力を抜けい、道満」
「無理、その、駄目なんだ、そこは、つまりその……んあぁっ!」
もう少し慣らしてやらねばならぬかと、腰を引いて気づく。そんなに乱暴にした覚えもないのに、白い敷布に深紅の花弁が点々と散っている。ふと、道満を貫いて弄んでいた手指に視線を移すと、そちらも朱に染まっていた。
「ああ、そういえば、痔持ちだったな」
「うるさい」
「まだ治ってなかったのか。婚礼の前に、ちゃんと診察を受けるがよいぞ」
勝手なことを言いながら、再び指を押し込む。今度は愛撫するというより、事務的ともいえる手付きでぐるりと掻き回す。すぐに、いくつかの病巣を探り当てた。
「だだっ……いだっ……つぅっ!」
「なるほど、これか。ふむ、擦れて破れてしまったようだ。済まぬことをしたな」
清明は素直に詫びると、その代わりとばかりに、痛みのせいか縮こまっている玉茎に触れて、やわやわと揉みしだく。
「あ、清明……」
その声色から何を察したか、道満の手首の縛めが解かれた。
無我夢中で清明の背に腕を回し、その胸に額を押し当てながら、与えられる愛撫に喘ぐ。受け入れることができないと分かっていても、先ほどくじり出された快楽が疼いて、気が狂いそうになる。
やがて『痛くてもいいから、やっぱり奥に欲しい』と口走ってしまいそうになった頃に、清明が「まあ、痔なら仕方ないな。修行が足らんと言いたいところじゃが、クリステルの婿には壮健でいて貰わねば、困る」などと言い出した。
「へっ……?」
「お前の、当初の予定通りじゃろう?」
先端を覆う薄紅色の皮が分泌された汁と擦れあって、くちくちと濡れた音を立てている。いや、先端だけでなく、それを包んでしごいている清明の手指までべっとりと濡らすほどだ。だが、まだ茎は軟らかく、手を離すとへたりと倒れてしまう。
「こういうことは初めてか? 手間のかかる奴じゃ」
清明が、仰向けに転がったままの道満の腰を跨いだ。刺し貫くことはできぬまでも、肌と肌が触れあい、吹き零れた体液を混ぜ合わせて、くちゅくちゅと淫猥な音をたてる。徐々に、陽根に『気』が集まっているのは、察する事ができた。
「そう、百会(ひゃくえ)から天の気を感じて、身体の中に流れ込む様を思い浮かべるのじゃ。わしが地の気を吸い上げて天へと返してやろう。道満、自我を捨てて、天地の気の巡りに身を委ねよ」
だが茎を刺激されればされるだけ、腹の奥の熱も共に膨らみ意識を朦朧とさせる。
「これ、聞こえておるか? しっかりせい」
ひたひたと頬を叩くも、道満の目は虚ろなままだ。清明は身を屈めると、陽根が奮い立たぬのに焦れて、道満の唇に軽く噛みついた。それを待っていたように、道満が口に吸い付いてくる。深く舌を絡めあい、飲み込みきれない唾液が顎を伝い首筋にまで流れるが、それを拭うこともなく尚も貪る。
「あ……駄目だ……っ」
何が駄目なのかと訝った清明が問い返そうとした時に、道満の身体が大きく爆ぜた。接している部分がじわっと温かくなり、生臭い匂いが立ちこめる。
「堪えられなかったのか。この未熟者」
置いてきぼりにされた口惜しさも込めて、ぽかんと頭を叩く。道満も精が抜けてようやく正気に返ったか、己の失態に唖然としていた。
「す、すまん、清明」
「わしは一向に構わんが、クリステルを満足させてやれぬのは困る。これも陰陽道の一理じゃ。初夜までには精進せいよ」
清明が跨いでいた道満の腰から降りると、手の甲で額を拭った。口調こそ平静を装っているが、清明も劣情を催していたのか頬が上気しており、全身、水を浴びたかのように大粒の汗の珠を浮かべている。道満は今さらのようにそれに気付いた。しかも、筋を浮かべて怒張したものは、天を仰いだままだ。
「その、俺だけよくなっちゃって、ゴメン。その、お前は」
「わしのことはよい。適当に処理するから、帰れ」
「帰れと言われても、あの、腰が抜けて」
それは事実だ。全身が綿になってしまったかのように、力が入らない。だが、実際には肉体的な疲労以上に、いいように弄ばれた挙げ句に暴発してしまった己の情けなさに気力が萎えて、起き上がることができなかった。
「ふん。ならば、そこで寝ておれ」
清明が枕元を指差した。その先には、いつの間にかは知らぬが、術を使って畳んだのであろう着物が積まれている。さらに指をツイッと動かすと、その懐から白い紙がふわりと抜け出した。ひらひらと蛾のように宙を飛び、清明の手の中に収まる。清明は褥に腰を下ろしたまま、それをかざすと「葛葉。伽をせい」と、ぶっきらぼうに命じた。
葛葉は、妖艶な美女に化けた狐の霊であり、清明に仕える数ある式神の一体でもある。
「仰せのままに」
衿を押し広げて肩を露わにすると、たわわな胸乳が現れた。だが、帯を解いて脱ぎ落とす寸前、その豊満な臀部の後ろにちろりと毛の固まりが見えた。それを慌てて片手で隠しながら「どう致しましょう」と尋ねる。
「雁が首でいい」
雁が首とは、いわゆる尺八のことだ。葛葉の視線がちらりと道満に注がれたが、すぐに思い直したようで「御意」と答えると、座っている清明の正面に腰を下ろし、身体を屈めた。分厚く塗られた白粉と口紅の匂いが濃く立ちのぼり、ぬるりと包み込んで来る。その快楽に思わず声を上げかけ、道満の存在を思い出したか、とっさに己の口を手で覆った。
道満は思い掛けない光景に、目を逸らすのがマナーだと頭では理解しつつも、視線が吸い付いて動けなくなっていた。女の頭が動き、えげつない水音がたつ度に、清明の呼吸が乱れる。
「ほほほ。この葛葉をお呼びになる前に、どんな悪戯をなさっていたのですか? そこの、道満様とお戯れだったのですか? へのこが最早、はち切れそうではありませぬか」
「無駄口を叩くな」
うふふと笑って、葛葉は再び根元まで吸い込んだ。そして異形のものに相応しく、まるで女陰のごとき蠕動と締め付けで主人を扱き上げ、愛撫する。清明は葛葉の頭を見下ろし、化け切れずに生え残り、ぴこぴこと動いている獣の耳も愛おしげに撫でてやった。それが嬉しいのか、黄色い尾がふわりふわりと揺れている。
道満はなぜか、その睦まじさが気に入らなかった。妬ましかったと言っても良い。ついさっきまで、その笑みと愛撫は自分に向けられていた筈なのだ。いや、葛葉もそれを自覚しているに違いない。ちろちろと清明の身体越しに視線を送ってくる。
「清明」
起き上がって呼び掛けると、その上体にしがみついていた。
「なんじゃ、催したのか? だから帰れと言うたに、ほんに仕様のない……お前も、葛葉に抜いてもらうか?」
「嫌だ」
「嫌じゃ」
なぜか、葛葉も口を揃えて拒む。
もちろん清明がそうせよと命じれば、式神である葛葉に拒否権など無いのだが。
「わしに、どうせいと言うのじゃ。まったく」
溜め息を吐きながらも、腰に葛葉を吸い付かせたまま、腕を回して道満の身体を抱き寄せてやると、子犬のように飛びついて、口元を舐めてきた。
「俺も、清明をヨくしてやりたいんだ」
「ふん、未熟者が何を言うか」
だが、道満の手が清明の胸元を這って敏感な部分に触れると、さすがに清明の身体もぴくんと小さく爆ぜた。尚もそこを撫で回そうとする手指を捕らえ、それ以上悪さをしないように指を絡める。その間も、葛葉は根元から先端まで舐めまわしたかと思うと、裏側に吸い付いてねっとりとなぞり、時折、ぎゅっと引き締まっている袋までちろちろと舌を這わせるなど、手管の限りを尽くしていた。
「どうせ、俺は未熟者だ」
「拗ねるな」
それでもお前はわしの親友であり、これからは我が弟にもなる、大切な存在だ……そう伝えたかったが、腰の奥の熱が爆ぜる感触に、一瞬、頭の中が真っ白くなった。とっさに、絡めている指にギュッと力がこもった。道満が、その手を握り返してくる。
やがて、清明の上体がずるずると脱力して崩れ、道満の腕に抱きとめられた。その包み込む腕の感触は、なかなか悪くないと、清明には思えた。多少、修行が足りてない未熟者だが、これならクリステルの婿としては合格点だ。そんなことを考えながら、ゆっくりと清明は意識を手放す。
鈍い頭痛を覚えながら、清明は目を覚ました。全身が軋むような感覚に訝りながら起き上がり、同じ布団に転がっている全裸の男と、己の大きな尾を枕にしている狐を見て、昨夜の乱行を思い出した。どうやらあのまま、道満も葛葉も、文字通り『精根力尽きて』眠ってしまったらしい。
雄の匂いと獣臭が室内にこもって、息苦しいほどだ。清明はとりあえず単衣を羽織ると(己もその臭気の発生源のひとつであることは棚に上げて)扇子を引き寄せてそれでパタパタと周囲を仰ぎながら、障子に歩み寄って大きく開いた。昨夜の雨が嘘のように空は晴れ渡っている。新鮮な空気が流れ込んでくるのを、肺いっぱいに吸い込む。それも、ただの深呼吸ではなく『導引』と呼ばれる特種な呼吸法を用いて、肺の空気をすっかり入れ替えると、生き返った心地がする。
だが、その匂いは肌にも染み付いているようだ。
「葛葉、起きろ」
名を呼ばれて、狐がピョコンと跳ね起きた。自分がすっかり元の姿に還っているのに気付いて、慌てて身を躍らせた。一瞬、煙のようにその身体が原子分解し、たちまち人間の女の姿に再構築される。
「おはようございます、清明様」
「うむ。そいつを叩き起こして、騒ぎになる前にあちらの屋敷に帰らせろ。わしは湯あみをしてくる」
「御意」
葛葉は畜生の脳ゆえか、それとも昨夜の奉仕に割り込まれた恨みでか、主人の命令を『文字通りに』実行して、道満とケンカになったようだが、清明もそこまでは関知しない。中庭に向かう途中で下男を見つけて、行水用のたらいに湯を張るよう命じた。
服を脱いで用意された湯に浸かり、手拭いで肌を擦る。そういえば接吻のし過ぎか、唇が腫れているような気がしなくもない。口付けを交わして……自分の腕の中で乱れて、果てていく姿、自分に向ける憎悪と思慕、そして満ち足りたように口元を綻ばせている寝顔も見た。もうあいつの見ていない姿など無いかもしれないと思うほどに……あとは、強いて言えば、雪隠の個室でいきんでいる姿ぐらいか。いや、そんな姿は見たくもないが……そんなことを己の唇に指を触れながらぐだぐだと考えていると「本日の江戸は爽やかな晴れ、ところにより突発的な雨が降るでしょう」という声と共に、ざぶっと頭から湯をぶっかけられた。
振り向くと、清明の妹にして、かつては人気女子アナウンサーでもあったクリステルが、手桶を片手に立っていた。
「なんだ、まだ天気予報ごっこか?」
どうせ頭も洗うつもりであったので、妹の悪戯を敢えて咎めることはしないが、それでも清明は多少、ムッとした表情を浮かべていた。
「お身体を流しましょうか」
クリステルはそういうと、兄の返事を待たずにその手から手拭いを取り上げた。しばしの間、黙々と兄の背中を擦っていたが、ふと「本当に、私は道満さんに嫁がなければいけないのですか?」と、囁きかける。
「何を今さら」
「子供の頃から一緒ですから、その、あんまり、そういう対象に思えなくて」
「結野家と巳厘野家を結ぶためじゃ」
この兄妹の間でもう、何回となく繰り返された問答であった。いつもと違うのは、清明が「まぁ、アイツもあれはあれで、愛いところもある。仲良くしてやれ」と付け加えたことだ。
「でも、道満さんに嫁ぐぐらいなら、私、兄上の方がいい」
「馬鹿を言うな。それでは巳厘野家との和平にならぬではないか」
「兄妹だからダメ、とは仰ってくださらないのですね」
クリステルが正面に回って、胸元も拭おうと手を伸ばしてくる。清明はその白魚の手を掴んで、手拭いを取り上げた。
「今後は、そういうことは、道満にしてやれ」
クリステルは「はぁい」と、おどけた口調で返事をしてあっさりと引き下がったが、ふと思い出したように振り向くと「道満さんが愛いところもあるって、一体、どういうところなんですか?」と尋ねた。
式神の性格が悪いのは、術者の躾が悪いからだ。道満は延々と歯磨きをしながら、そんなことを考えていた。いくら相手の気に飲まれて流されたとはいえ、自分が男相手、しかもあのかつてのライバル清明なんぞに口吸いをした挙げ句、舌まで絡めていたとか、誠に信じられぬ。まさにおぞましい。しかも、あの畜生はそれを逆恨みして、噛みつくの引っ掻くの。
「道満さん」
背後から呼び掛けられて、不意を突かれた道満は咳き込んだ。歯ブラシも吹き飛ばす勢いでゲェゲェ吐き出してから、口を濯いで振り向く。
「ク、クリステルか。どうした、こんな朝早くから何用じゃ?」
「道満さんて、ピンクのお帽子を被っているんですって? 兄上から聞きました」
「はぁ!?」
一瞬、何の事か理解できず、目を白黒させるしかない。だが、自身の玉茎の形状を指しているのかと察し、そんなことを花嫁に教えた清明に、改めて殺意を覚える。だが、その後に「素敵なコーディネートですね。男性のピンク色って、とても着合わせが難しいのですけど」という台詞が続いたため、どうやら都合良く誤解しているらしいとも気付いた。
「えっ? あ、そうそう、コーディネートね、ハハハ」
必死で笑って誤魔化しながら、道満が己の頭を掻く。その衿元がはだけて胸元が露わになると、クリステルの細い眉が吊り上がった。
「道満さん。昨夜は女性と寝ていたのですか? 私との婚礼を控えているというのに」
「へっ!?」
女性じゃなく、君の兄上と……と弁解しかけて、それも言うべきでないと気付き、道満は言葉を失う。
「だって、その、お化粧の匂いと、噛みついた痕。まぁ、引っ掻き傷まで」
「あっ……!」
それは、葛葉につけられたケンカの傷だ。だが、湯あみをする前であったせいで、情事の残り香と白粉の香りを漂わせていては、如何せん説得力が無い。
なんとか「それは誤解だ」と必死で説き伏せ、クリステルも(とりあえず表面的には)納得したのだが、心の奥底にはしこりになって残ったのかもしれない。もちろん、この一件だけが原因ではなかろうが、クリステルは嫁入りしても心を開くことも、肌身を許すこともなく、結果として破局に至ったのであった。
(了)
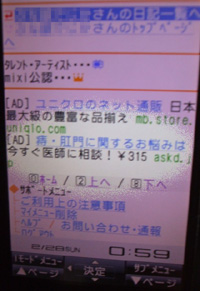 【後書き】陰陽師編をアニメで見ているうちに、なんとなく『痔だから仕方ないよね』って理由で生暖かく接してもらって凹む道満ってよくね!? という、なんとも救いようのないアイデアに萌えを感じて、一気に書き上げてしまいました。 【後書き】陰陽師編をアニメで見ているうちに、なんとなく『痔だから仕方ないよね』って理由で生暖かく接してもらって凹む道満ってよくね!? という、なんとも救いようのないアイデアに萌えを感じて、一気に書き上げてしまいました。
ちなみに、右の画像は、このアイデアを晒した某SNSの日記(タイトルは『やべぇイボ痔に萌えた!』)を表示したページの携帯画面……よく見ると痔の広告が! ちょっ、そんな親切イラネェ!!!!(爆笑)
これに気付いて撮影してくれた北宮さん、愚ッジョブです。
初出:10年02月28日
←BACK |
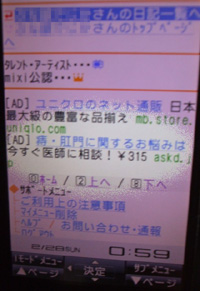 【後書き】陰陽師編をアニメで見ているうちに、なんとなく『痔だから仕方ないよね』って理由で生暖かく接してもらって凹む道満ってよくね!? という、なんとも救いようのないアイデアに萌えを感じて、一気に書き上げてしまいました。
【後書き】陰陽師編をアニメで見ているうちに、なんとなく『痔だから仕方ないよね』って理由で生暖かく接してもらって凹む道満ってよくね!? という、なんとも救いようのないアイデアに萌えを感じて、一気に書き上げてしまいました。